漫才という芸のあり方を考えるとき、よく「偶然の雑談」という言葉で定義されることがあります。つまり、あたかも事前の打ち合わせなどなかったかのように自然に始まった会話が、思わぬ展開を見せて観客を笑わせる、という形です。
もちろん現実には、すべてのセリフはネタ合わせで決められているものですが、それでも舞台上では「今初めて聞いたようなリアクション」を演じることが重要です。そこにこそ漫才らしさが宿るという考え方が根強くあります。
「練習してみよう」で始まるコント漫才の違和感
その観点から見ると、「ちょっと練習してみよう」といった流れで突然コントに入る形式には、「本当に自然な雑談なのか?」という疑問がどうしても生じます。
観客の中には、こうした展開にわずかな違和感を覚える人もいるでしょう。なぜなら、リアルな日常会話の中で、急に別人になりきるような展開はほぼ起こりえないからです。それでも、「漫才とはそういうもの」として受け入れられつつあるのが現在の状況です。
導入を省略するスタイル:サンドウィッチマンの例
この「導入を飛ばすスタイル」の代表例として、サンドウィッチマンの漫才が挙げられます。彼らの名作「ピザの出前」のネタでは、冒頭からいきなりコントパートが始まる構成になっています。
伊達「世の中ね、興奮することが色々ありますけど、一番興奮するのは、出前の遅いときですよね」
富澤「間違いない」
このやりとりのあと、すぐに「ピザの配達員とお客さん」のコントに入っていきます。もしも現実世界で同じような流れが起きたら、「え?何の話?」と混乱してしまうはずですが、漫才という文脈の中ではこれが成立するのです。
あえて違和感を無視するという選択
なぜこのようなスタイルが受け入れられているのか。それは、観客も「これは漫才」という前提で舞台を見ているからです。サンドウィッチマンのような人気コンビは、あえて導入の自然さを捨てて、「とにかく早くネタに入りたい」「1個でも多くボケを入れたい」という発想で構成しているように思われます。
ヤーレンズのネタ構成にもそれは表れており、「練習してみよう」などの導入こそあれど、比較的スピーディーにコントに入る傾向があります。「違和感を最小限にしつつ、テンポよくボケに入る」というバランス感覚が求められているのです。
M-1が推し進めた「競技漫才」化
こうした背景には、M-1グランプリの影響も無視できません。決勝戦ですらわずか4分という短い持ち時間の中で、いかに無駄なくボケを詰め込むかが勝敗を分ける要因となっています。
この「1秒たりとも無駄にしない」という考え方が浸透し、ネタ全体が競技のように論理的に構築されるようになった結果、導入の自然さよりも「とにかく早く笑いに入ること」が重視されるようになってきました。

令和ロマンの髙比良さんがその代表例で、緻密な構成力とボケ密度の高さが評価されています。今や多くの若手漫才師が「競技」としてのM-1を分析し、戦略的にネタを設計しているのです。
まとめ
漫才には本来「偶然の雑談」のような自然さが求められてきましたが、近年ではそのスタイルも大きく変化しています。特にM-1グランプリのような短時間で勝負が決まる舞台では、導入部分を短縮し、すぐにコントパートに入るスタイルが主流になりつつあります。サンドウィッチマンやヤーレンズに代表されるように、「あえて違和感を無視し、1秒でも早くボケに入る」という構成が現代の漫才における一つの答えになっているのです。今後は「自然な導入」と「効率的な構成」の両立が、新しい漫才スタイルの鍵となるかもしれません。

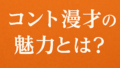

コメント