今回は、「自分たちはしゃべくり漫才とコント漫才、どちらが向いているのか?」と迷っている方に向けて、コント漫才に向いているコンビの特徴について整理してみたいと思います。
もちろん、どちらが優れているという話ではなく、それぞれの持ち味や相性によって、ネタの活かし方が変わってくるということです。特に、舞台でどのような演技をするのが得意か、どういう構成に面白みを感じるかといった観点で、自分たちに合ったスタイルを見つける参考になればと思います。
① キャラクターを演じるのが得意・好き
まず最初のポイントは、「さまざまなキャラクターを演じるのが好き・得意」という要素です。舞台上で自分とはまったく異なる人格になりきることに抵抗がなく、それをむしろ楽しめるタイプのコンビは、間違いなくコント漫才向きと言えるでしょう。

たとえば、職業を変えたり、性別や年齢の設定をいじったりすることで、ネタの世界観は一気に広がります。お笑いでしかできない“なりきり”の自由さを活かすことができれば、観客にとっても強烈なインパクトを残すことができます。
代表例として、2024年M-1決勝に進出したマユリカの中谷さんは、女性キャラクターを演じることでも知られています。その演技が特別にリアルというわけではありませんが、「振り切って演じる」という姿勢がネタ全体に説得力と笑いを与えています。お芝居のうまさではなく、“キャラとして面白いかどうか”が最重要なのです。
② ネタのバリエーションを広げたいコンビ
次に、コント漫才は「ネタの幅を広げたい」「いろいろな設定に挑戦したい」と思っているコンビにも向いています。しゃべくり漫才は自分たちの会話の延長線で展開するスタイルが多いため、どうしてもテーマや展開が似通ってしまうことがあります。
一方、コント漫才は設定ごとにまったく異なる世界観を作れるため、「今日はお化け屋敷のスタッフ」「次は新入社員と社長」「その次はコンビニの深夜バイト」など、多様なジャンルに挑戦しやすくなります。
たとえば、2本のネタを披露する大会やライブがあるとき、1本をしゃべくり・もう1本をコントにしてみるだけで、「このコンビ、幅広いな」「何でもできるな」という印象を持ってもらいやすくなります。こうした印象は、審査員や観客にとっても好印象につながることが多いです。
③ とにかくボケ数を増やしたいコンビ
3つ目の要素として、「とにかくボケの量を増やしたい」というコンビには、コント漫才がとても相性が良いです。しゃべくり漫才は、自然な会話としてスタートするため、ネタの導入にある程度の“助走”が必要になります。
「最近さ〜」や「この前思ったんだけど…」のようなセリフで日常の話題を始め、そこから徐々に笑いを積み上げていく必要があるため、最初の30秒〜1分は“仕込み”のような時間になりがちです。
その点、コント漫才では最初に「今日は○○の役でやります」と設定を提示するだけで、いきなりボケに突入できるケースが多くなります。導入でモタつくことなく、序盤からテンポよくボケを重ねていけるため、笑いの回数をとにかく稼ぎたいコンビにとっては大きな武器になるでしょう。
例えば、サンドウィッチマンのように「いきなり設定に入る」ことで、1秒でも早く笑いを取りにいくという構成は、近年のM-1など時間制限のある舞台でも非常に有効です。
「型」にとらわれすぎず、自由な発想を
ただし、最も大切なことは「しゃべくり漫才か?コント漫才か?」という分類にあまり縛られないことです。最近の漫才では、会話の中にちょっとした演技を織り交ぜる“ミックス型”のネタも増えており、明確に区分けできないスタイルもたくさん登場しています。
大切なのは、「自分たちがやっていて楽しいか」「観客が分かりやすくて笑えるか」という2点だけです。最初から型にハマろうとするよりも、まずは自由にネタを作って試してみる方が、自分たちのスタイルを見つけやすいのではないでしょうか。
まとめ
コント漫才に向いているコンビには、主に「キャラクター演技が得意または好き」「ネタの世界観を広げたい」「とにかくボケをたくさん入れたい」といった傾向があります。ただし、どちらのスタイルが正解ということはありません。むしろ最近では、ジャンルの境界がどんどん曖昧になってきており、“自分たちにとって面白い”と感じるスタイルを見つけることが何より大切です。いろいろなタイプのネタにチャレンジしてみることで、もしかしたら今まで誰もやってこなかった、新しい漫才スタイルが見つかるかもしれません!


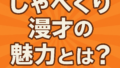
コメント