「さあネタを書こう!」と思い立ってPCを開いたり、ノートを広げたりしたものの、いざ書こうとすると何も浮かばない――そんな経験がある方は多いのではないでしょうか?
私自身もココナラ経由で漫才制作の依頼を受ける際、「テーマは完全にお任せで!」というご要望をいただくことがあります。自由度が高い分、どこから手を付けるべきか悩むというのはプロでも日常茶飯事です。
そこで今回は、「ネタのテーマをどうやって決めていくか?」という初歩的だけどとても重要なポイントを、具体例を交えてご紹介します。
まずは「好きなジャンル」で攻めてみよう
最初の一歩としておすすめなのが、「自分の好きなジャンルからテーマを決める」というアプローチです。詳しく知っていること、熱く語れるものは、それだけで武器になります。
学校でのスピーチや会社のプレゼンでも、原稿を棒読みしている話より、ちょっと噛みながらも“自分の言葉”で語る人の方がずっと伝わってきますよね?それと同じで、自分の本音や感情がにじむテーマの方が、観客に届きやすく、説得力が生まれます。

具体的には、スポーツ、音楽、アニメ、旅行、ゲーム、地元の話など、本当に何でもOK。M-1などの大会に出場する予定がある方は、公序良俗に反する内容や特定の個人・団体への攻撃にならないよう注意が必要ですが、基本的には自由です。
マニアックなテーマは武器にもなる
「いや、自分の好きなものはマイナーすぎて誰にも伝わらないよ…」と尻込みする方もいるかもしれません。でも、実はそこにチャンスがあります。
確かに、マイナーすぎるテーマを“あるあるネタ”として展開するのは難しいかもしれませんが、その“伝わらなさ”を逆手に取ったネタ構成なら可能性が広がります。
たとえば、クリケットのような日本ではあまり馴染みのないスポーツをテーマにした場合でも、次のような切り口なら成立します。
ボケ「俺は昔からクリケットが大好きでさ」
ツッコミ「だいぶマイナーなスポーツだけどな」
ボケ「今日は世界のクリケット選手を野菜で例えて紹介していきたい!」
ツッコミ「たとえもマニアックか!!」
ネタとして成立するだけでなく、「なんだこれ!」という意外性で印象に残る可能性すらあります。内容よりも“構造の工夫”で笑いは作れるのです。
メジャーな題材には“既視感”のリスクも
逆に、「誰にでも伝わるネタを…」と考えて、例えばスーパーマーケットや学校を舞台にしたネタにする場合、それ自体は安心感がある分、ありがちになってしまうというリスクも潜んでいます。
多くの人が作りがちな題材だからこそ、似たような展開、似たようなボケになってしまい、「どこかで見たことあるな…」と思われてしまう危険性が高いのです。もちろん、構成や視点が秀逸であれば十分戦える題材ではありますが、個性を出すには工夫が必要です。
“自分ごと”であることが最大の強み
好きなものや詳しいものは、ネタのなかに「自分ごと」がにじみ出やすくなります。情報の正確さよりも、「そこに熱があるか」「実感があるか」の方が、観客の心に届くという点で、笑いの“熱伝導率”を高めてくれるのです。
調べながらでもネタは書けますが、“自分の言葉”で語れる内容こそが、結果的にもっとも強いネタになりやすいのです。
まとめ
漫才のネタ作りで最初につまずくのが「テーマ選び」です。そこでまずおすすめしたいのが、「自分の好きなものから考える」というアプローチです。マニアックすぎると不安になるかもしれませんが、逆にそれを活かす構成を工夫すれば、唯一無二のネタになる可能性も十分にあります。ありふれた題材よりも、自分だけが語れる内容の方が観客に刺さることも多く、“熱”や“実感”がネタの強みとなっていくでしょう。迷ったらまずは「語りたいこと」から考えてみる。それがネタ作りの第一歩です。
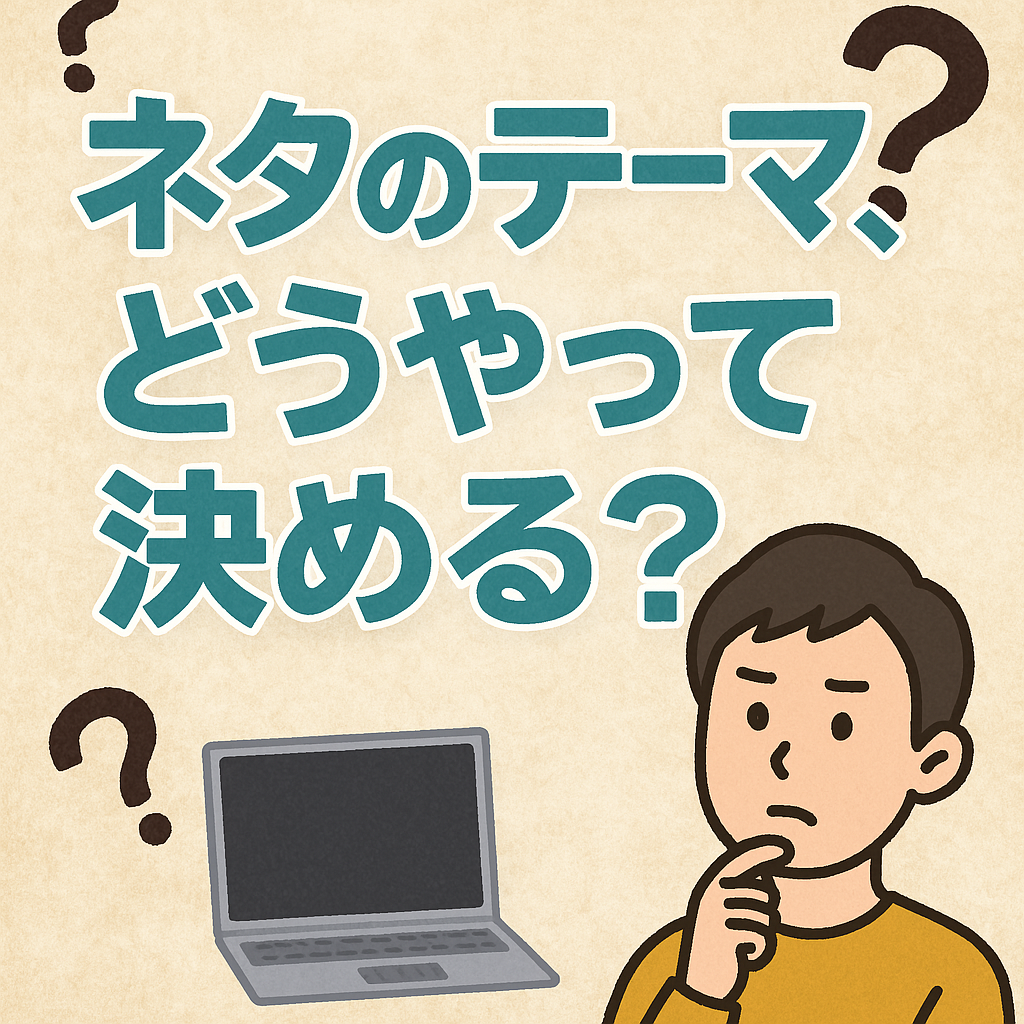
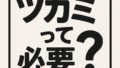

コメント