漫才には「ツカミ」と呼ばれる冒頭の一ボケがあります。観客の緊張をほぐし、舞台と客席の空気をつなぐ役割を担うものですが、ツカミを入れるかどうかは悩みどころです。今回は、その効果と使い方について考えていきましょう。
たとえば、2023年のM-1グランプリで令和ロマンが披露した1本目のネタには、登場直後にしっかりとツカミが仕込まれていました。
ふたり「どうも。よろしくお願いします!」
くるま「松井ケムリさんという方。髭とモミアゲがつながっております。なんでつなげてるんだろうって疑問がわきますよね?これ簡単でして、毛で自分の顔をぐるりと囲うことによって、顔の内側を日本から独立させようとしてるんですよ」
ケムリ「そんなわけねえだろ!」
このやり取りで客席は一気に笑いに包まれ、そのまま本ネタの「少女漫画」パートへとスムーズに移行しました。
ツカミは「場を温める」だけじゃない
ツカミの主な目的は、「まず一笑いをとって場の空気を和らげる」ことです。しかしそれだけでなく、観客に「このコンビはこういう雰囲気です」と印象を伝える役割も持っています。
特に、観客にとって初見のコンビである場合、最初の10秒〜20秒は「どんなネタをやるんだろう?」という警戒心や緊張感が強く、笑う準備が整っていないことが多いです。そこで一発ツカミを入れることで、「あ、面白そうなやつらだな」と興味を引く効果が生まれます。

令和ロマンのツカミも、本ネタとは直接関係がないにもかかわらず、次のような印象を観客に与えています。
- くるまさんのボケはロジカルで独特な角度がある
- ケムリさんのツッコミは歯切れよくテンポが良い
- コンビ間の力関係としてくるまさんが主導している
つまり、笑いと同時にキャラクターの提示がなされており、観客がネタに入りやすくなる効果があるのです。
ツカミが本ネタとつながっていないとダメ?
「ツカミとネタの本筋がつながっていないと不自然では?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、むしろツカミは“ネタから独立したフリーゾーン”と考えた方が自然です。
ただし、まったく関係のない雰囲気やキャラで始めてしまうと、観客が混乱することもあります。重要なのは「キャラや世界観の方向性にズレがないか?」という点です。
例えば、普段はクールで理知的なキャラで進める漫才師が、ツカミだけテンションの高いおバカキャラを演じていたら、観客は違和感を覚えます。それが「ネタ全体のノイズ」になるリスクがあるのです。
「東京ホテイソン」の例に学ぶ
2020年のM-1で決勝進出した東京ホテイソンのたけるさんは、「いーや〇〇!!!」というインパクトあるツッコミでブレイクしました。テレビのロケなどでもこのツッコミを効果的に使っており、彼らの代名詞ともなっています。
では、もし漫才のツカミ部分で「いーや〇〇!!!」を使わず、全く普通のテンションで始めたらどうなるでしょうか?笑いがとれたとしても、せっかくの“武器”を捨てているようにも見えます。
ツカミは“コンビの魅力を凝縮する1ボケ”と考えると、むしろツカミの中でこそ自分たちらしさをしっかり見せるべきなのです。勢い任せで入れるのではなく、「ネタとのつながり」「キャラとの整合性」を意識するのがベストです。
ツカミを入れるべきか迷ったときは?
とはいえ、すべての漫才にツカミが必要かといえば、そんなことはありません。ツカミでスベると、その後の空気を立て直すのが非常に難しくなってしまうリスクもあります。
「自信がないなら入れない」のも一つの判断ですし、「ウケないリスクがあるなら、せめてキャラ提示に特化したセリフを最初に置こう」といった発想もありです。
あくまでツカミは選択肢の一つ。大事なのは、「このネタにツカミを入れた方がトータルでよくなるか?」という視点で判断することです。
まとめ
漫才における「ツカミ」は、単なる一笑いを取るための手段ではなく、観客にキャラや空気感を伝える“自己紹介”としての役割も果たしています。うまくハマれば、ネタの世界観への導入がスムーズになり、その後のボケも受けやすくなるという好循環が生まれます。ただし、キャラと噛み合わない内容や、ウケなかったときのリスクもあるため、慎重な判断も必要です。とはいえ、アマチュアならば挑戦あるのみ。やってみたいツカミがあれば、どんどん試してみましょう!そこにあなたのコンビだけの“ツカミ力”が見つかるかもしれません。
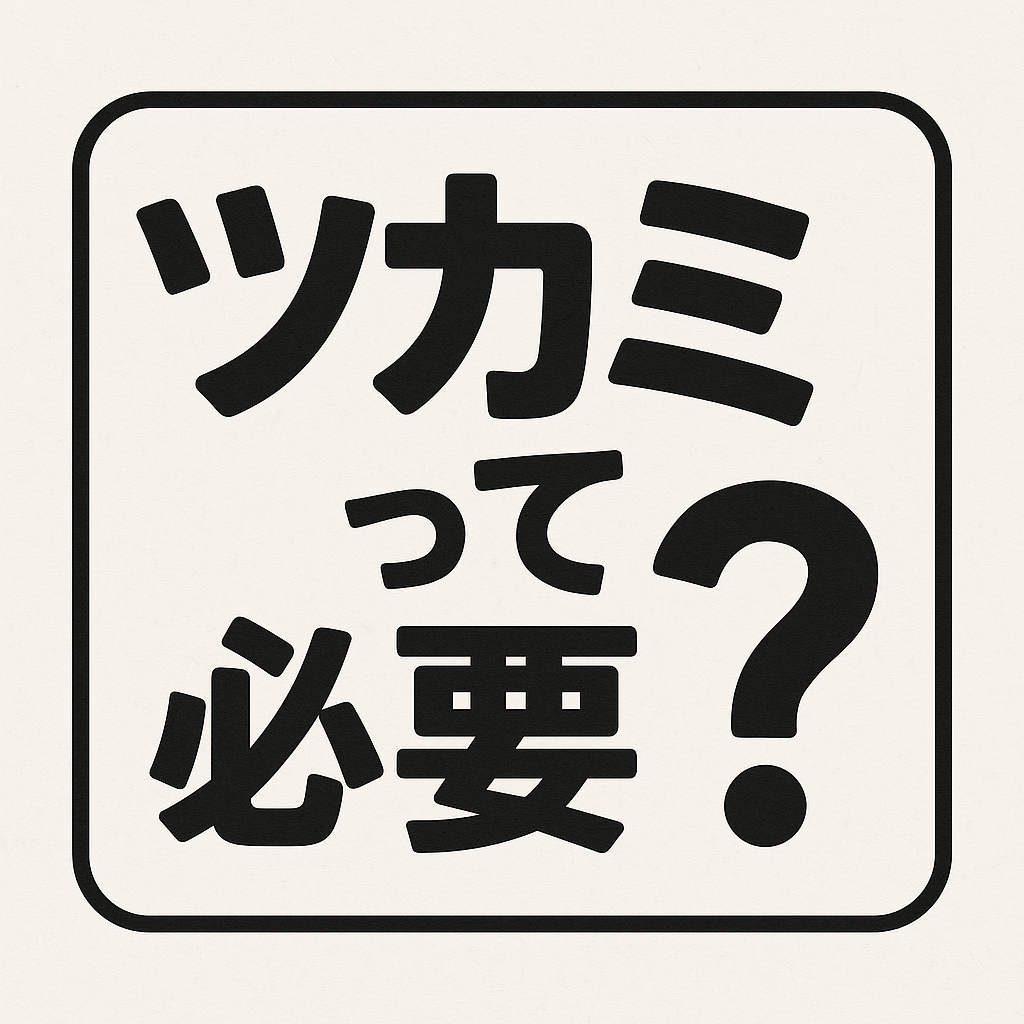

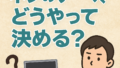
コメント